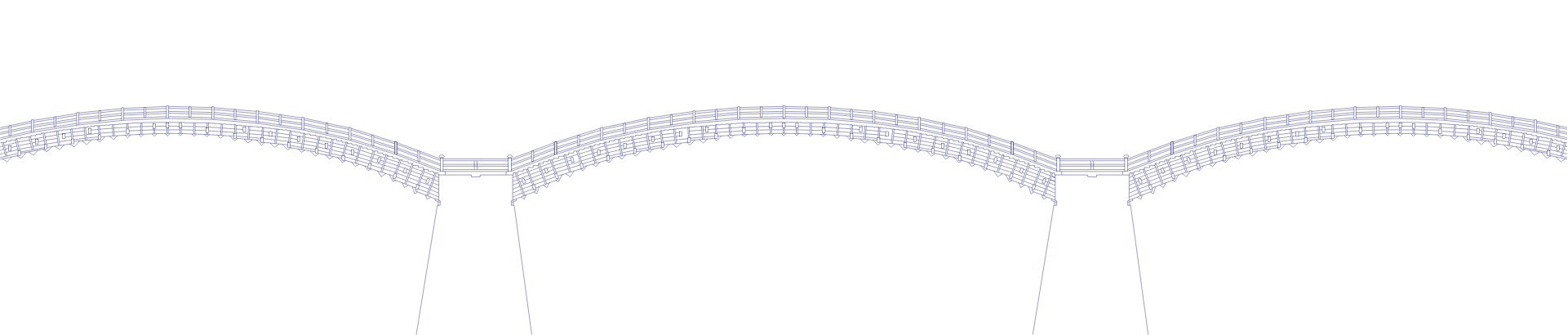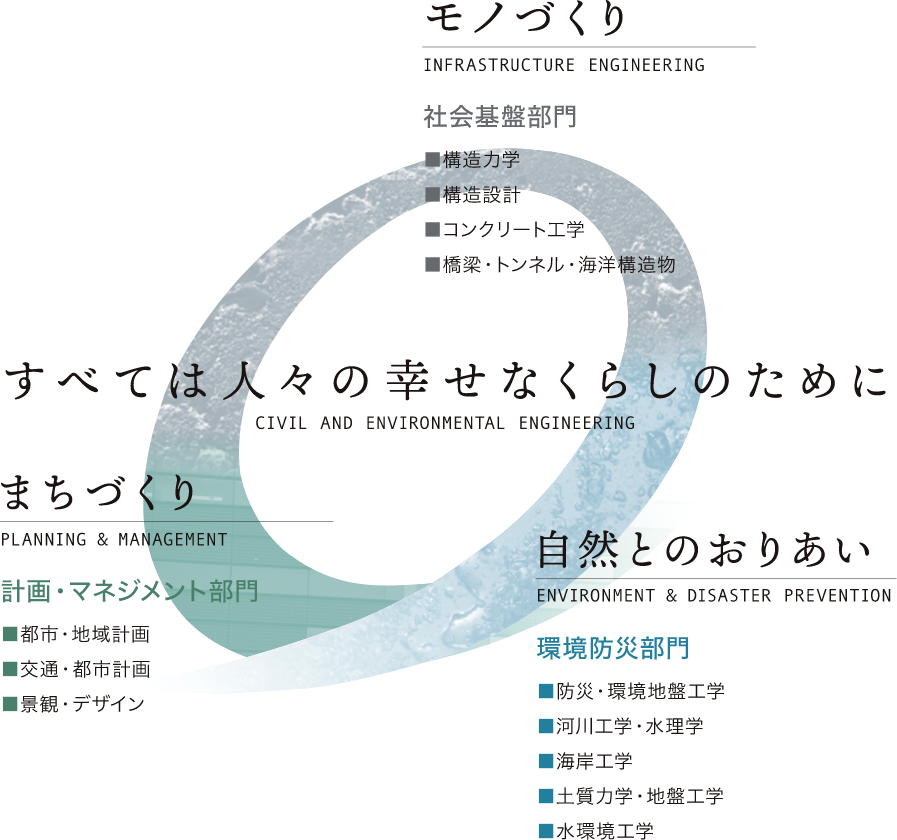
社会環境工学とは
社会環境工学は、地球的視点から自然環境の保全、人間環境の向上、人間社会の安全等を工学的に取り扱う学問です。技術者倫理に基づいて、人間が安全で文化的な生活を送るために必要な社会基盤を整備し、人間が自然との協調と共生の中で生活するための方策を実現することが社会環境工学の重要な役割です。
社会環境工学科の前身は土木工学科です。土木工学科は早稲田大学理工学部百年の歴史のなかで、60年間にわたり伝統を蓄積してきました。その伝統の上に2003年度より社会環境工学科へと改称するとともに、 Civil and Environmental Engineeringという英語名が示すように、市民生活と自然環境とが密接に関係しあった工学へと展開しました。さまざまな現代的課題のもとで、現在と未来の豊かな人間社会の構築を考える学科が、社会環境工学科です。
また社会環境工学科は創造理工学部に属します。創造理工学部は、他に、建築学科・環境資源工学科・経営システム工学科・総合機械工学科・社会文化領域から構成され、人間の生活に最も近い創造的な工学を追及する学部です。